私は自然が好きで(自然が好き、という言葉は幅が広すぎる気もするが)、気晴らしに近場を散策することがある。目に入る様々な生物たち。鳥類、昆虫、植物、はてしなく小さな菌類。色鮮やかなビビットカラーの花々も美しいが、控えめにぽつんと咲いている花に特に目を惹かれる。
そして、その花の名前すら頭に出てこないという事実に嘆息する。そこに存在しているのに呼びかける名前が分からない。名前が分からないので考えの軸となるきっかけすら掴めない。そのことが何処か失礼なものに感じ、居心地が悪くなる。
行きつけの本屋さんに「生物を分けると世界が分かる(岡西政典先生著)」が置かれていた。安心と信頼のブルーバックス。帯紙に「私たちは、この地球のことをまだ何も知らない」との記載。この文言に惹かれすぐに手に取った。
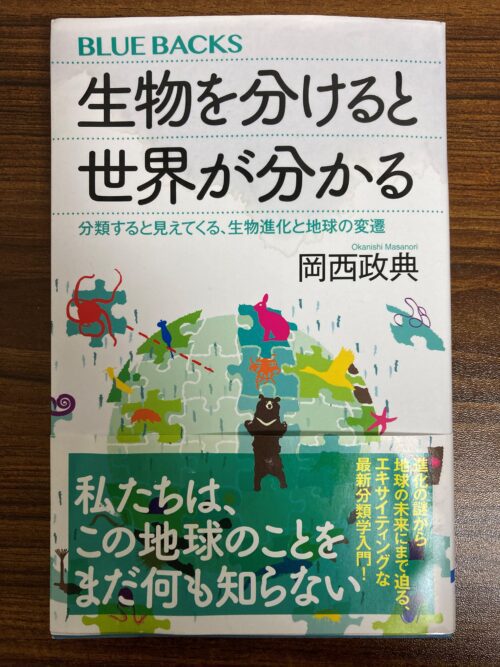
分類学は、学生時代にもっと取り組んでいればよかったな、と思う分野である。
分類学は生命を考える礎となると思う。物事は名前を与えられ(定義され)、そのうえで分類されカテゴライズされた後に議論が進む。
本書は分類学に詳しくない私でも楽しく読み進めることができたが、特に印象的だったのは、最終章(第6章)に書かれていた「分類学がなぜ必要なのか」という問いに対する筆者の答え。
分類学の進展がない世界は豊かなものではないと、分類学者である筆者は断言する。私は特に下記が心に残った。
分類学は、日常生活における私たちの視点を確実に広げてくれている。世界の解像度を高めてくれている、と言い換えることができるかもしれない。
岡西政典『生物を分けると世界が分かる』講談社 p213
(略)
分類学的なフィルターを通し、それらを共通の名前で認識することで初めて、私たちはその生物を理解できる。そしてそれらが棲む地球のことを理解できるのである。
分類学がなぜ必要かについては、さまざまな意見が提示されて然るべきだと思うし、有用性という観点からも重要な分野だと思う。本書でも記載があったが、COVID-19が猛威を振るう現在、生態系を記述する分類学の有用性は明らかである。
ただ、私は上記の引用内容が分類学の最も根源的な要請だと思う。
私は、知らないものは知りたいと思う。知ることにより、過去の知識、経験との有機的な繋がりを見せて、視界が急に広がる。知ることにより、自分の知らないことがかえって浮き彫りになる。ぼやけていたものがくっきりと鮮明となり、知/未知の境目が明らかになる。その境目をぐぐっと拡げていくことに喜びを感じる。
往々にして、研究は(生活に)どのように役立つのか?で評価される。身近なものに当て嵌めるとイメージが容易である。勿論重要な部分であり、実学的な視点は決して軽視されるべきではないが、「知の豊かさ」という観点からは、知的好奇心を満たすような研究も幅広く行われてほしい、と心から思う。
しきりに議論されてきている内容だとは思うけれども。